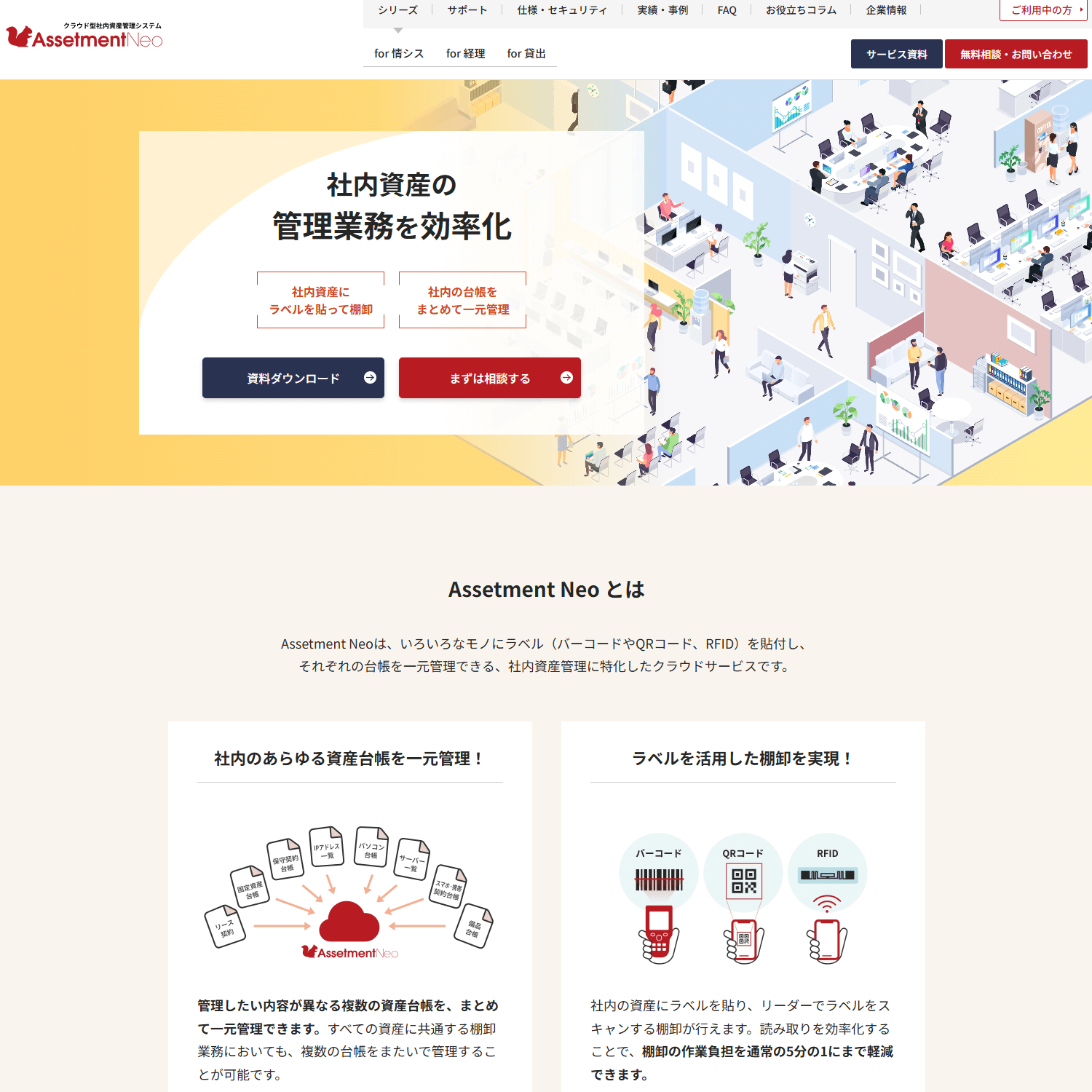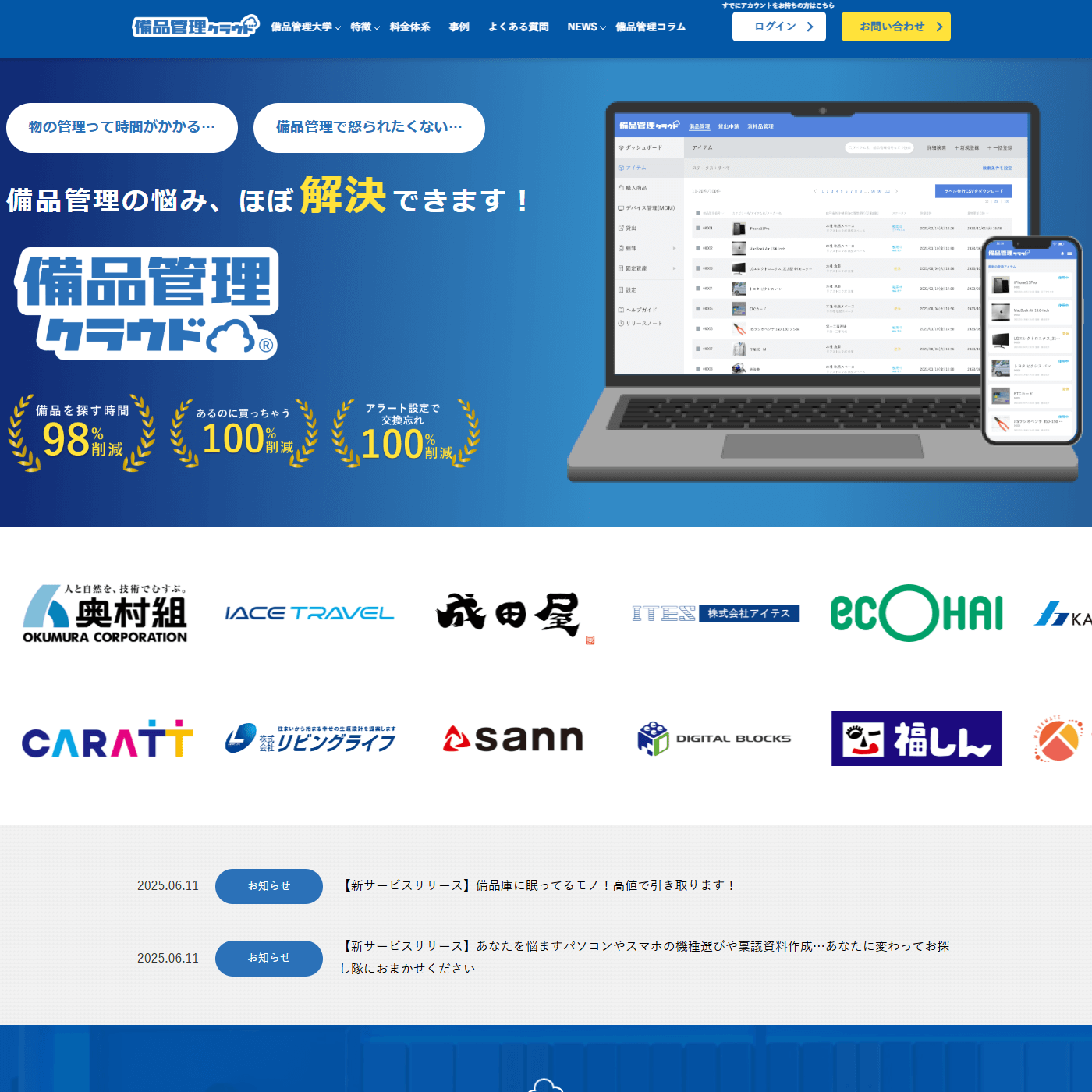企業において、物品の在庫や備品を正確に把握・管理することは、業務の効率化やコスト削減に直結する重要な業務のひとつです。なかでもエクセルを使った物品管理は多くの企業が導入しており、導入コストを抑えたい現場で根強い人気があります。そこで、今回はエクセルによる物品管理のメリット・デメリットついてくわしく解説していきます。
物品管理をエクセルで行うメリット
エクセルはMicrosoft Officeの基本ソフトのひとつで、ほとんどのパソコンに標準搭載されています。そのため、特別な準備をしなくてもすぐに利用できる手軽さが大きな魅力です。とくに物品管理においては、表計算ソフトであるエクセルの基本的な機能を活用することで、在庫数の記録、出入庫の履歴、棚卸結果の集計などを自由にカスタマイズできる点がメリットといえるでしょう。
また、エクセルは数式や関数を活用することで、単純な在庫表以上の管理が可能です。たとえば、一定の在庫数を下回った場合に色を変えてアラートを表示したり、月ごとの使用実績を自動でグラフ化するなどの機能を組み込むこともできます。
これにより、現場に即した柔軟な運用ができ、業務の属人化を防ぐことにもつながります。さらに、エクセルは導入コストがかからず、初期投資を抑えたい企業にとって非常に経済的です。
既存のパソコンで作業できるため、専用のソフトやクラウドサービスを契約する必要もありません。日頃からエクセルを使い慣れている社員がいれば、特別な教育コストも不要です。
物品管理をエクセルで行うデメリット
一方で、エクセルによる物品管理には、運用上の課題も多く存在します。最大のデメリットは、手作業による管理が中心となるため、入力ミスや転記ミスが起こりやすい点です。たとえば、在庫数を手動で更新している場合、誰かが更新を忘れたことで在庫情報にズレが生じ、誤発注や品切れの原因となる可能性があるのです。
また、ファイルの共有に関しても課題があります。複数人で同時にエクセルファイルを編集する場合、ネットワークドライブ上で操作する必要があり、誤って上書きしてしまうリスクや、古いデータが残ってしまうリスクが伴います。共有体制が整っていないと、いつ誰が更新したのかを把握するのが困難になり、トラブルのもとになりかねません。
さらに、データ量が増えてくると、エクセルの動作が重くなり、管理が煩雑になるケースもあります。とくに、数千件以上のデータを扱うようになると、フィルタ機能や検索機能では対応しきれず、データの抽出や分析に時間がかかることもあるでしょう。こうした作業負担がかさむことで、本来の業務に支障をきたすリスクが出てきます。
エクセルで行う物品管理には限界がある
エクセルは多機能で柔軟性が高い一方で、あくまで汎用的な表計算ソフトであり、物品管理に特化したツールではありません。そのため、エクセルの運用には限界があることを理解しておく必要があります。たとえば、リアルタイムの在庫状況の把握や、バーコードやQRコードを使った入出庫管理には対応していません。こうした機能が必要な場合は、手作業による補完や他ツールとの連携が必要になり、かえって非効率になることもあるのです。
また、エクセルファイルは個人のパソコンやネットワークドライブ内に保存されることが多く、データのセキュリティ面でも不安が残ります。誤って削除してしまったり、第三者によって不正に書き換えられるリスクがあるため、管理体制には細心の注意が必要です。
さらに、データの更新履歴が見えにくいため、誰がどのタイミングで修正を加えたのかがわからなくなり、トラブルの原因にもなるでしょう。さらに、業務が拡大して拠点や部署が増えると、エクセル管理では全体を網羅するのが困難になります。
それぞれの部門が個別にファイルを管理していた場合、情報の一元化ができず、全社的な物品の流れを把握しにくくなります。こうした状況では、物品管理にかかる手間やコストが増えるだけではなく、情報のズレや誤解も生じやすくなるのです。
また、社外への帳票提出や内部監査の際にも、エクセルベースでは信頼性に欠けると判断されるケースもあるでしょう。このように、エクセルでの物品管理には一定のメリットがあるものの、業務の拡大や多拠点対応といった環境変化に耐えうる柔軟性や拡張性には限界があります。
近年では、こうした課題を補う手段として、クラウド型の物品管理システムを活用する企業も増えてきています。専用ツールの導入によって、精度の高い管理や情報共有を実現することが可能です。一定規模以上の組織や、精度の高い物品管理が求められる現場では、やはり専用のシステムを導入するほうが効率的といえるでしょう。